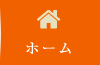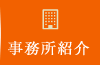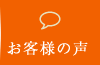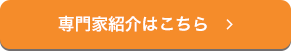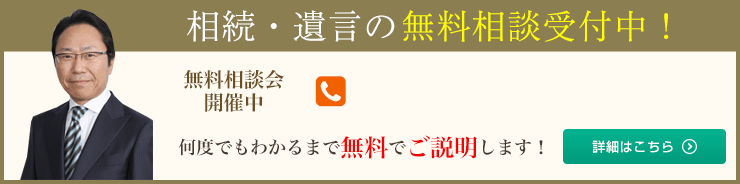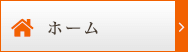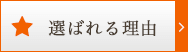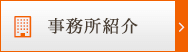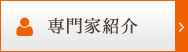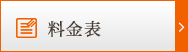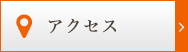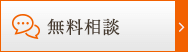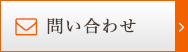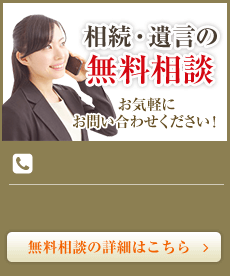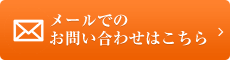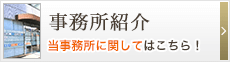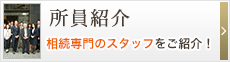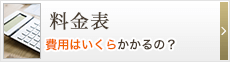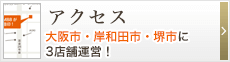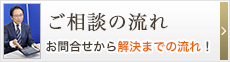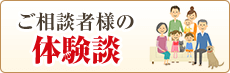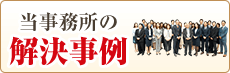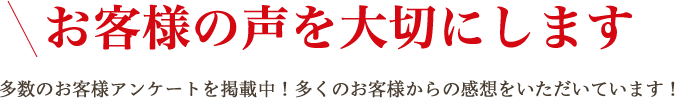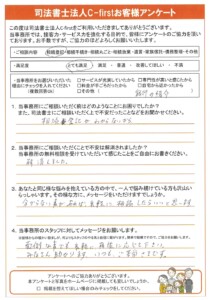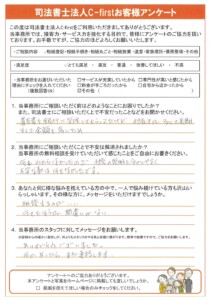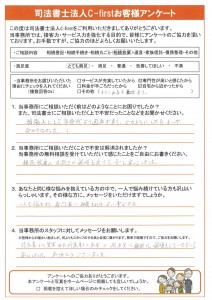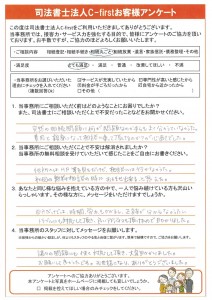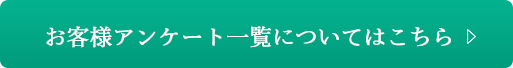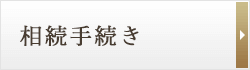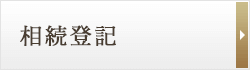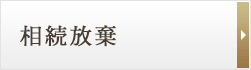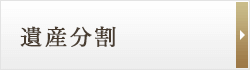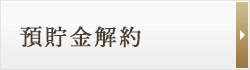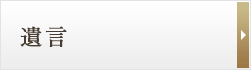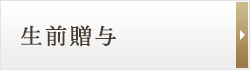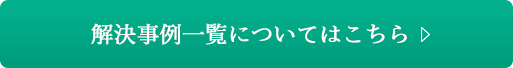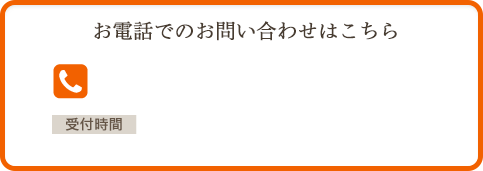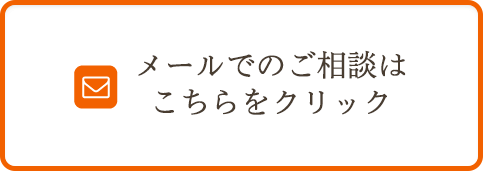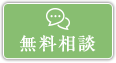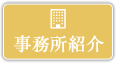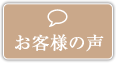前妻がいる場合の相続!前妻の子は相続権がある?相続の専門家が解説

被相続人(夫・父親)に前妻や前妻との間の子どもがいることがあります。
生前に被相続人から聞いていて知っていたケースもありますが、全く知らなかったということもよくあります。
前妻やその子どもを全く知らなかったご家族は、突然のことで混乱してしまいますよね。知っていたとしても面識はないことが多いですから、相続で揉めたりしないか不安になるかと思います。
まずは前妻やその子どもの相続に関する権利を理解することが重要です。
前妻とその子どもは遺産を相続できる?

結論から申し上げますと、前妻に相続権はなく、前妻との子どもには相続権があります。
前妻は過去に配偶者でしたが、すでに婚姻関係を解消しているため、法律上では他人同然の扱いとなります。
前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。
前妻の子が法定相続人であるということは、前妻の子を除外して遺産分割協議を行えないということになります。
前妻の子どもの相続分はどれくらい?
前妻の子どもは、法定相続人となります。
前妻の子は、現在の配偶者の子と同等の権利を有します。
そのため、遺産相続順位は第1位です。
現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。
下表は、法定相続人の順位と相続割合を示しています。
ちなみに、配偶者(後妻)は必ず法定相続人です。
| 法定相続割合・順位 | |
|---|---|
| 第一順位(子ども) |
配偶者2分の1 子ども2分の1 |
| 第二順位(被相続人の父母) |
配偶者3分の2 父母3分の1 |
| 第三順位(被相続人の兄弟姉妹) |
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
遺産の2分の1を子どもたちが相続できます。
前妻の子と配偶者の子は、同等の割合で被相続人の遺産を相続する決まりです。
子どもが2人以上いた場合、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けることになります。
例)前妻の子どもの相続割合の計算方法
【法定相続人】
配偶者、配偶者との子3人、前妻の子1人
【財産額】
8,000万円
【計算方法】
8,000万円×1/2=4,000万円(子全員の相続割合)
4,000万円×1/4=1,000万円
子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けますから、4分の1です。
前妻の子どもは1,000万円を相続することとなります。
前妻の子は「遺留分」がある
前妻の子は被相続人である父親と法的にも親子関係にあるため、法定相続人となれました。
そのため、法定相続人に認められている遺留分もあります。
遺留分とは、法定相続人に認められた一定の財産を受け取る権利です。
「前妻の子に財産を1円も渡さない」は覆される
被相続人である父親が、
「前妻の子には相続させない」
「後妻である現在の配偶者の子に全財産を渡す」
と遺言書に残していても、前妻の子が遺留分侵害額請求の申立をした場合、前妻の子は遺留分を受け取れることになります。
前妻の子が相続放棄をした場合は、1円たりとも財産を受け継ぐことができなくなりますが、これを強要することはもちろんできません。
配偶者(後妻)の子どもに財産を多く残す方法

前妻の子は法定相続人であり相続の権利があることは理解できても、例えば被相続人との関係性や自分の子どもを想う気持ちから納得できなこともあろうかと思います。
配偶者(後妻)のお子さんであれば、生前に対策をされることで、受け継ぐ合計財産額を多くすることは可能です。
遺言書を作成しておく
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「遺言書の作成」があります。
基本的には、父親(被相続人)が作成した遺言書の内容が優先されます。
配偶者(後妻)との子どもに多く残す旨を残しておけばよいのです。配偶者に多く残すことも可能です。
ただし、前妻の子の遺留分には注意してください。
具体的には、前妻の子は法定相続分の1/2を遺留分として相続する権利があります。
父親の死後に揉めてしまうのは面倒ですので、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくとよいです。
生命保険を活用する
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生命保険金」の活用があります。
生命保険金は、原則、遺産分割協議や遺留分の対象にならないためです。
受取人を配偶者の子ども(あるいは配偶者)に指定しておくことで、生命保険金を全額受け取ることができます。
生前贈与を行う
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生前贈与」があります。
注意点は、被相続人が亡くなった日から遡って10年以内に贈与された財産については、遺留分の対象となってしまうことです。
生前贈与については制度がいくつもあり、場合によっては損をしてしまうこともあります。
生前贈与をうまく活用するためには専門家にご相談されることをおすすめします。
財産を配偶者名義にする
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「財産の名義変更」があります。
前妻の子が相続できるのは、被相続人の財産だけです。
つまり、被相続人と配偶者が築いた共有名義の財産については、配偶者名義にすることが有効です。
配偶者が亡くなった際の相続で、配偶者の子どもが相続する遺産の対象とします。
連絡をしたくない…前妻の子がいる相続は司法書士に相談

前妻やその子どもの存在を知らなかった場合はもちろん、知っていたとしても初対面の方と相続やお金について話し合うのは気が引けます。
なるべくなら連絡を取ったり直接会ったりするのは避けたいですよね。
当事務所に相続手続きをまるっとお任せいただければこのようなお悩みは解決できます。
前妻やその子どもがいたケースで、司法書士がお手伝いできることをご紹介します。
前妻や前妻の子への連絡を代行
戸籍収集をして愛人やその子どもの住所を特定します。
前妻の子(子が未成年であれば前妻)に対して連絡をとります。遺産分割協議に参加してもらうためです。
下記の内容で書面を作成します。
・相続が発生した旨
・相続財産の内容
・法定相続分
・遺産分割案
この連絡ややりとりを司法書士に依頼することができます。
遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成
被相続人のご家族と前妻やその子だけの話し合いでは、遺産分割で揉めてしまうことが多いです。
相続の専門家である司法書士にお任せいただければ、第三者の立場で遺産分割のアドバイスをすることが可能です。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
手続きを全て代行
前妻やその子とのやりとりだけでなく、相続によって発生する手続きをお任せいただけます。
プランにもよりますが、銀行や証券会社での相続手続き、不動産の手続きなど煩雑かつ複雑な相続手続きをフルサポートいたします。
遺言内容のアドバイス・遺言書の作成
被相続人が生前にできる対策として「遺言書の作成」をおすすめしております。
遺留分を考慮した、ご家族にとって最適な遺産分割についてアドバイスいたします。
相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。
| 相続財産の価額 | サポート料金 |
|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 |
| 500万円超~5000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
| 3億円超~ | 2,904,000円~ |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5.5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1 種類につき11 万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円加算させていただきます。
※相続放棄をされる方がいる場合は別途費用が必要です。
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450 円、750 円)、登記簿謄本(例:480 円) 等
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を
業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。